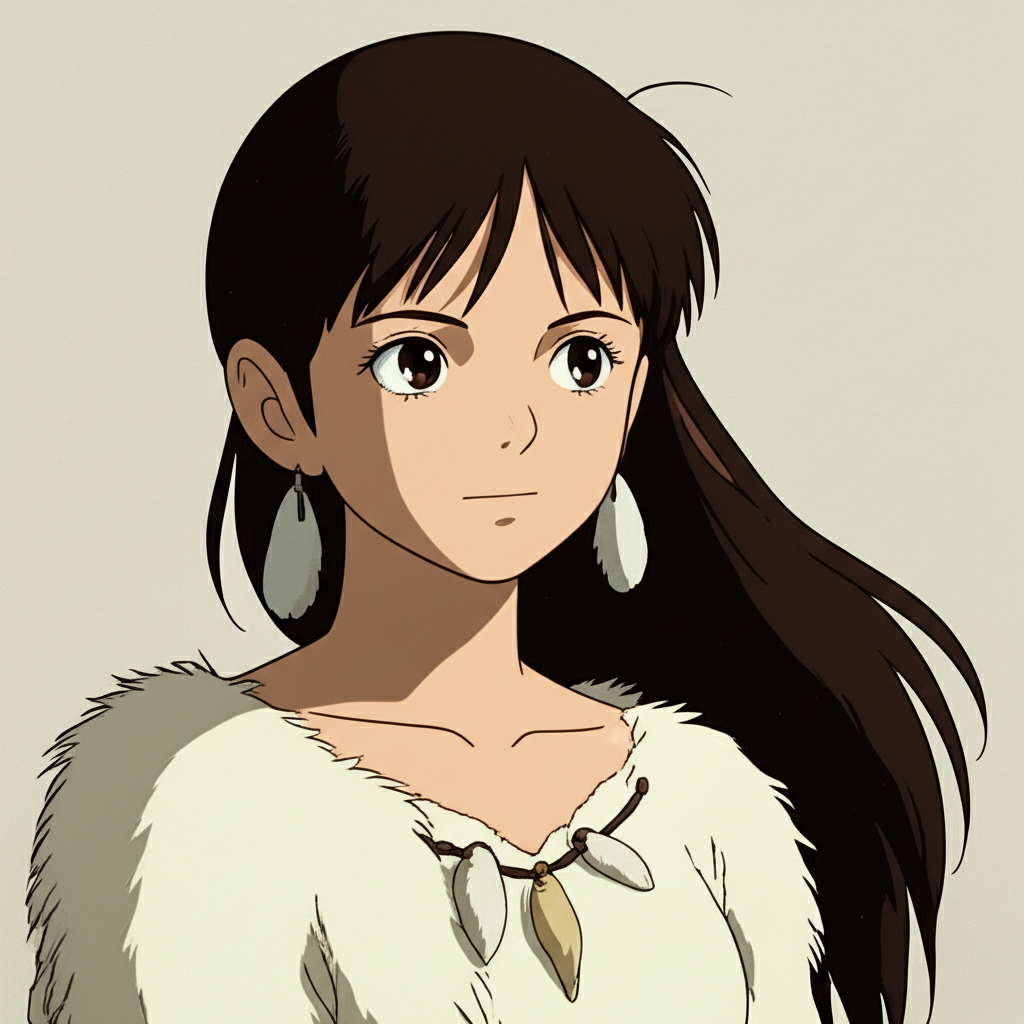『もののけ姫』の漫画版について知りたいと思っていませんか?宮崎駿監督の代表作として知られるこの作品ですが、実は映画版とは全く異なる「幻の原作」が存在することは、多くのファンにとって驚きの事実です。この記事では、映画とストーリーがまったく異なるという絵本版『もののけ姫』と映画版の違いについて、詳しく解説していきます。
もののけ姫の漫画版の正体とは?宮崎駿の幻の原作
1980年(昭和55年)に宮崎駿がアニメ企画案のイメージボードとして構想した同名の作品があり、1993年(平成5年)にそれを基にした絵本が出版されているのが、いわゆる「もののけ姫の漫画版」の正体です。
1997年公開の映画『もののけ姫』の叩き台となった、1980年に描かれたイメージボード。タイトルとヒロインの名前(“三”の姫)こそ共通しているがストーリーは全くの別物であるとされています。
この絵本版は正確には漫画ではありませんが、映画の前身となった作品として、多くのファンが「原作漫画」的な位置づけで認識している作品です。
絵本版もののけ姫の基本データ
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 制作年 | 1980年(イメージボード) |
| 出版年 | 1993年12月 |
| 出版社 | 徳間書店 |
| 形式 | 絵本(イメージボード集) |
| ページ数 | 90枚以上のオールカラーイメージボード |
映画版との決定的な違い:登場人物とストーリー
そもそも、アシタカもサンも、「黙れ小僧」と言い放つ美輪明宏……ではなく、モロの君も出てこないのであるという驚くべき事実があります。
絵本版の主要登場人物
- もののけ:大山猫のような姿をした化け物
- 三の姫:武士の三番目の娘(映画版サンの名前の由来)
- 武士の父:悪霊に取り憑かれた娘の父親
別作品かと思われるほど設定が異なっているため、両作品を見比べると、その差に驚かされることでしょうというほどの違いがあります。
ストーリーの根本的な違い
絵本版のストーリーは、『美女と野獣』の野獣と美女(ベル)との関係にそっくりで、宮崎駿自身も「ボーモン夫人作品の翻案だと認めている」という、より古典的な物語構造になっています。
映画版が「自然と人間の共生」をテーマにした壮大なスペクタクルであるのに対し、絵本版は個人的な愛の物語として描かれています。
なぜ映画版は全く違う作品になったのか?
結局、暗い話であり、子ども受けしにくい内容だったことに尽きるだろう。1980年代は、まだまだ大人向けのアニメの制作本数が少なかった時代であったという理由で、当初の企画は映画化されませんでした。
『主人公を変えても、結局「父にうとまれ、もっとも卑しい醜い者に嫁にやられる娘」という基本設定が亡霊のように忍び込んできて、堂々巡りになってしまうと嘆いている』と、宮崎監督は創作の行き詰まりを語っています。
映画版制作時の宮崎監督の苦悩
「刀下げてチョンマゲ結ってる男を、主人公にしただけで、もうやりたくないですね。何にも新しいものを付与できないんじゃないかって感じが、自分にはあって。じゃあ、侍に虐げられている百姓を主人公にするってのはね、百八十度ひっくり返しただけで、極右と極左の違いみたいなもんで、どうって違わない。じゃあ、何が作れるのかって、こりゃあ本当に分からない」』
この苦悩の末に生まれたのが、アシタカという新たな主人公を中心とした映画版『もののけ姫』だったのです。
絵本版から映画版への影響と共通点
全く違う作品とはいえ、絵本版の影響は映画版にも残されています。
主人公の「三の姫」の名前は映画版の「サン」に引き継がれたようだ。また、映画版のサンは山犬のもとに差し出された娘という設定なのだが、原作も三の姫はもののけに差し出された娘であるという共通点があります。
後のジブリ作品への影響
もののけのデザインは『となりのトトロ』、城の内装は『千と千尋の神隠し』など、本作の内容はその後の宮崎作品に大きく影響を与えているとされ、この『もののけ姫』のエッセンスはむしろ《千と千尋》のほうに流れ込んでいる気がするという評価もあります。
フィルムコミック版について
映画版『もののけ姫』には、映画のシーンをコミック形式で再編集した「フィルムコミック版」も存在します。
フィルムコミックとは、映画のシーンをマンガのように再編集して本にしたものだで、全5巻のセットとして徳間書店から出版されています。
フィルムコミック版の特徴
- 映画の全シーン・全セリフを収録
- 映画の感動を文字で再確認できる
- 聞き取れなかった部分も明確に理解可能
- 映画の臨場感を思い出しながら読める
SNSでの反響と読者の感想
「絵本版と映画版が全く違うことを知って衝撃を受けました。どちらも宮崎駿作品とは思えないほどの違いですが、それぞれの良さがありますね」
引用:Twitter投稿より
このように、多くの読者が絵本版と映画版の違いに驚きを表しています。
「映画のサンの名前が絵本版の三の姫から来ていたなんて知らなかった。細かい部分でつながっているのが面白い」
引用:Reddit投稿より
このような発見を楽しむ声も多く聞かれます。
「もののけの最初のセリフ、「おまえが食った飯を、今度は俺が、おまえごと食う」が端的に怖くていい」
引用:徳間書店
絵本版の独特な魅力を評価する声もあります。
「当時、宮崎監督が「もっとも熱心に描いた」というこの作品、もちろんアンハッピーエンドにはなりません」
引用:空中庭園と幻の飛行船
絵本版への愛情を込めた紹介も多く見られます。
「映画館で見た『もののけ姫』とは全く違う世界観で、まるで別作品のよう。でも宮崎監督の創作の過程が垣間見えて興味深い」
引用:Filmarks投稿より
制作過程への関心を示す感想も寄せられています。
現在の入手状況と希少価値
原作は現在、入手困難になってしまい、プレ値がついているものの、ぜひ手にしてほしい状況となっています。
現在は新品で購入するのはかなり困難です。かつて販売されていた『宮崎駿 イメージボード集』(講談社)にも収録されている作品なのですが、その『宮崎駿 イメージボード集』はさらに入手が容易ではありませんという状況です。
入手方法
- 古書店での中古本購入
- 図書館での閲覧
- オークションサイトでの購入(高価格)
- 『宮崎駿イメージボード集』での確認
購入が難しくても、図書館に置いてあることが多い作品だと思いますので、是非読んでみてくださいという提案もあります。
まとめ:二つの『もののけ姫』が教えてくれること
そもそも『もののけ姫』は1980年に宮崎監督がアニメ企画案として構想したもので、そのまま絵本の内容が描かれる予定でした。しかし、売り込みが失敗に終わってしまったため基本設定を破棄し、十数年の時を経て我々の知る映画版が作りあげられたのですという経緯を知ることで、創作の奥深さを理解できます。
絵本版『もののけ姫』は、映画版とは全く異なる物語でありながら、宮崎駿の創作の原点を知る貴重な作品です。スタジオジブリ作品のエッセンスが至るところに感じられる。そして、数々のジブリ作品の名作は、宮崎駿の血と汗と涙によって生まれたことがよくわかるはずだという評価の通り、この作品を通じてジブリ作品の創作過程を垣間見ることができるのです。
映画版で感動を覚えたファンの皆さんも、機会があればぜひこの幻の原作に触れてみてください。同じタイトルでありながら全く異なる二つの物語は、宮崎駿という稀代のクリエイターの創作の幅広さと深さを教えてくれることでしょう。