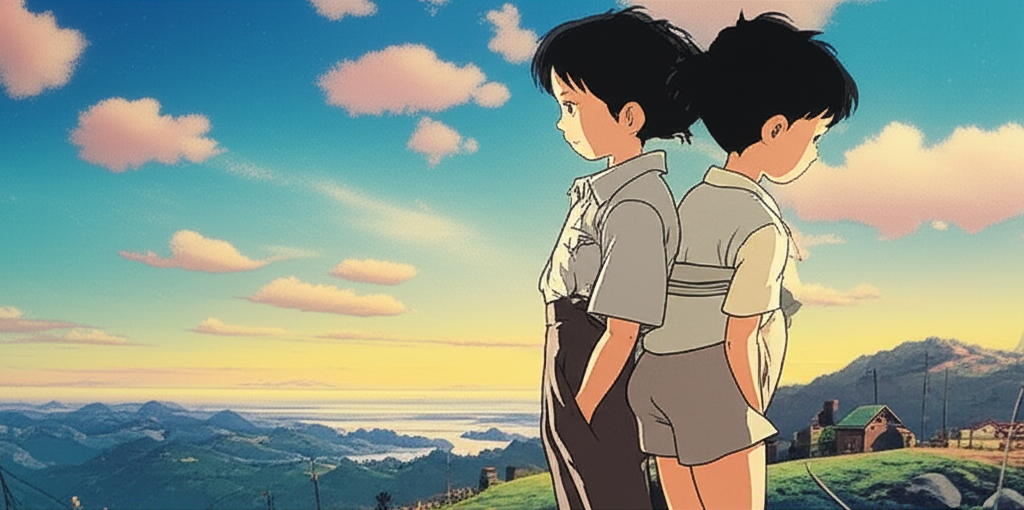火垂るの墓のエンディング曲と音楽の真実
「火垂るの墓」の音楽は、「となりのトトロ」とちょっと異なる映像から作曲家の〈顔〉が完全には見えてない。純粋に映像とストーリーが重く心に迫る。音楽は〈絵〉の重さを支えるプラットフォームとなっている印象だ。と専門家が語るように、この作品の音楽は映像と深く一体化しています。


結論として、火垂るの墓には明確な「主題歌」や「エンディング曲」は存在しません。代わりに、映画の音楽を担当したのが日本を代表する作曲家、間宮芳生(1929年~)による美しいBGMと、挿入歌として使用された「埴生の宿(はにゅうのやど)」が、作品の感動を支えています。
間宮芳生による音楽の構成
映画本編の音楽は間宮芳生が担当し、「焼野原」他、全18曲収録されているサウンドトラックには以下のような楽曲が含まれています:
| 楽曲名 | 役割 | 特徴 |
|---|---|---|
| 節子と清太~メインタイトル | オープニング | 鉄琴の美しい3拍子の旋律 |
| 焼野原 | 戦災シーン | 戦争の悲惨さを表現 |
| 母の死 | 感動的なシーン | 深い悲しみを表現 |
| ほたる | 蛍のシーン | 短い命の美しさ |
| ふたり~エンドタイトル | エンディング | 静かな余韻を残す |
映画音楽としての特殊性
映画と音楽と結びつく時、映像はより雄弁になる。視覚と聴覚が同期して、頭の中で記憶として固着化するという効果を狙い、高畑勲監督と間宮芳生は従来のアニメとは異なるアプローチを取りました。
火垂るの墓の音楽は、キャッチーなメロディーではなく、物語の感情に寄り添う「環境音楽」のような役割を果たしています。これが、一般的なアニメ映画とは異なる深い感動を生み出している理由なのです。
挿入歌「埴生の宿」の深い意味
作品中で最も印象的な歌として使用されているのが「埴生の宿(はにゅうのやど)」です。蓄音機で流れる音楽、イギリス民謡の「埴生の宿(はにゅうのやど)」です。幼い妹、節子の火葬前に、兄、清太が節子を回想するシーンで使われていました。
「埴生の宿」の詳細情報
- 原題:Home, Sweet Home
- 作曲者:ヘンリー・ローリー・ビショップ (Henry R. Bishop, イギリスの作曲家)
- 作詞者:ジョン・ハワード・ペイン (John Howard Payne, アメリカ合衆国の俳優・劇作家)
- 日本語訳詞:里見 義(さとみ ただし、1824 – 1886)
「埴生」とは土の上にむしろを敷いて寝るような粗末な小屋という意味で、まさに節子と清太が暮らしていた小屋のことです。この歌詞の選択は偶然ではなく、物語のテーマと深く関連しています。
楽曲が持つメッセージ性
「Home, home, sweet, sweet home(故郷よ、愛しき故郷よ)」という歌詞は、幼くして戦争で両親と家をいっぺんに失い、兄妹2人きりで戦禍を耐え生きようとしたストーリーなだけに、グッときますと多くの視聴者が感じています。
間宮芳生という作曲家の背景
間宮 芳生さん(まみや・みちお=作曲家)11日、肺炎のため死去、95歳というニュースが2024年12月に報じられ、日本音楽界の巨匠がこの世を去りました。
間宮芳生のプロフィール
1929年生まれ。東京音楽学校(現・東京藝術大学)卒業。バルトークの影響を受け、民俗音楽の研究に取り組み、日本民謡、ジャズやアフリカ民俗音楽などの素材と、クラシック技法と融合させた特徴を持つ作品も多いという経歴を持つ、日本現代音楽界の重要人物でした。
特に注目すべきは、間宮芳生が戦争体験世代の作曲家であることです。1929年生まれの間宮芳生、作曲家が塊のように生まれた日本作曲家黄金世代に属する。同世代の作曲家は濃淡あるにせよ、戦争・終戦がその後の人生を決める重要な契機であったことは間違いないという背景が、作品に深い説得力を与えています。
高畑勲監督との関係
高畑勲監督作品では「太陽の王子 ホルスの大冒険」「セロ弾きのゴーシュ」「柳川堀割物語」にも、楽曲提供しているように、両者は長年にわたって協力関係にありました。
サウンドトラックの特殊な構成
「サウンドトラック集」と銘打たれていたので、純粋な楽曲だけが入っていると思っていました。しかし聞いてみると、映画版の内容をCD向けに収録したもので、いわゆるドラマCDですという特徴があります。
サウンドトラック収録内容
このアルバムは、音楽だけでなくセリフや効果音も含め、映画の音をまるごと収めた文字通りのサウンドトラック盤。名シーンをセレクトして収録されています。
- A面:主にオープニングから中盤のシーン
- B面:後半からエンディングまでのシーン
- 特徴:純粋な楽曲ではなく、映画の音声を含むドラマCD的な構成
SNSで話題になっている投稿と反応
“思い出すだけで胸を締め付けられます。⚓️ 埴生の宿も わが宿 玉のよそい うらやまじ のどかなりや 春の空 花はあるじ 鳥は友”
このような投稿からは、「埴生の宿」が多くの人の心に深い印象を残していることが分かります。特に戦争で家族を失った兄妹の物語と重ね合わせると、歌詞の意味がより深く響きます。
“火垂るの墓のオリジナルサウンドトラックCDでは思いっきりセリフがかぶって台無しになっている。しかしなんと「節子―「火垂るの墓」メモリアルアルバム [単行本]」の付録に付いている8センチCDに「節子と清太〜メインタイトル」がセリフなしで収録されています”
引用:Amazon レビュー
このレビューは、純粋に音楽だけを聴きたいファンの気持ちを代弁しており、楽曲のみの収録を求める声が多いことを示しています。
“郷愁を誘う旋律に乗せて英語の歌詞、というところが流石ジブリ映画のセンスが光るところですが、特に「Home home, sweet sweet home」と歌う部分が、幼くして戦争で両親と家をいっぺんに失い、兄妹2人きりで戦禍を耐え生きようとしたストーリーなだけに、グッときます。”
このコメントは、楽曲選択の巧妙さと、物語との絶妙なマッチングを評価しており、多くのファンが感じている感動を言語化しています。
音楽が作品に与える影響力
火垂るの墓の音楽は、単なるBGMを超えて、物語の核心部分を支える重要な要素となっています。
映画音楽としての革新性
本公演はストーリー、映像、音楽、いずれの起点であっても、名作となりえている理由、当時のこと、映像と音楽、物語の結びつきなどに自然と、かつ、気軽に思いを巡らせられる仕掛けが多々あると専門家が分析するように、この作品の音楽は多層的な構造を持っています。
- 環境音楽的アプローチ:キャッチーなメロディーよりも雰囲気重視
- 歴史性の重視:当時の音楽文化を反映した楽曲選択
- 感情的な深み:視聴者の心の奥底に響く構成
現在でも続く評価
映画発表から30余年、間宮芳生による同映画音楽をオーケストラ演奏&朗読、そして画像で披露する音楽詩「火垂るの墓」初演が2023年に開催されるなど、現在でもその音楽的価値が高く評価されています。
別の視点から見るエンディングの意味
一般的なアニメ映画とは異なり、火垂るの墓には明確な「エンディング主題歌」が存在しないことで、逆に深い余韻を残します。
「ふたり~エンドタイトル」の効果
「ふたり~エンドタイトル」という楽曲名からも分かるように、清太と節子の絆を最後まで表現した構成となっています。歌詞のある主題歌ではなく、純粋な器楽曲で作品を締めくくることで、視聴者それぞれが感じた感情をそのまま持続させる効果があります。
イメージアルバムとの関係
いわゆるサントラではなく、そのプロトタイプ的なイメージアルバムです。間宮芳生さんの映画使用曲の原型はもちろんのこと、他の二人の作家の曲も良いですという制作過程から、間宮芳生、佐藤允彦、吉川和夫の3人の音楽家が綴る「戦争」への思い、そして主人公の幼い兄妹・清太と節子の物語をイメージしたアルバムが先に制作されていました。
まとめ:音楽が紡ぐ永遠の物語
火垂るの墓にはポピュラーな意味での「エンディング曲」は存在しませんが、間宮芳生による深遠なBGMと「埴生の宿」という挿入歌が、作品に計り知れない深みを与えています。
野坂昭如の作品『火垂るの墓(1967)』の文章と、その映画化されたアニメ(1988)。観た人は多いと思います。アニメのエンディングのテーマは「埴生の宿」でした。我々の世代の多く人は、涙せずにはいられなかった、と思いますという感想が示すように、この作品の音楽は単なる娯楽を超えた芸術的価値を持っています。
間宮芳生の音楽は、戦争の悲惨さと人間の尊厳、そして家族愛という普遍的なテーマを、言葉を使わずに雄弁に語りかけます。それこそが、この作品が35年以上経った現在でも多くの人々に愛され続けている理由なのです。
火垂るの墓の音楽を理解することは、この作品の真の価値を理解することに他なりません。映画を観返す際は、ぜひ音楽にも耳を傾けてみてください。そこには、間宮芳生と高畑勲監督が込めた深いメッセージが隠されているはずです。