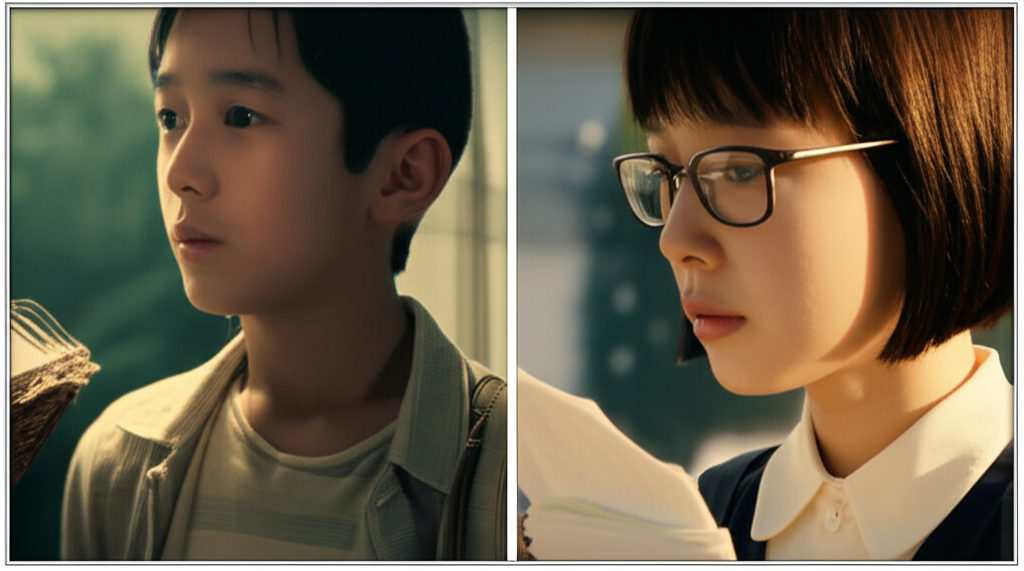清太がクズと言われる理由:結論
火垂るの墓の清太がクズと言われる最大の理由は、戦時中という極限状況において「働かない」「感謝しない」「プライドが高い」という現代的な価値観を持っていたからです。


多くの視聴者が指摘する清太の問題行動は以下の通りです:
| 行動 | 問題点 | 当時の常識との乖離 |
|---|---|---|
| 働かない | 14歳で労働可能年齢にも関わらず勤労奉仕をしない | 当時は小学生でも大人の手伝いが当然だった |
| 家事を手伝わない | おばさんに全ての家事を任せきり | 男女問わず家族総出で家事をするのが普通 |
| 感謝の気持ちを示さない | 食事を出されても無愛想 | 戦時中の貴重な食料への感謝は必須 |
| 社会との協調を拒む | 集団生活に馴染もうとしない | 全体主義の時代に個人主義は異端 |
なぜ清太はこのような行動を取ったのか?詳細な理由
1. 裕福な家庭で育った「お坊ちゃん」だった
清太の父親は海軍大尉という高級将校で、家庭は非常に裕福でした。そんな環境で育った清太は、疎開先の西宮の親戚のもとでも働かずに毎日節子と遊んだりして過ごしていました。戦時中の大変な時期に子どもを2人も引き取っただけでも大変なのに、そんな清太におばさんが腹を立てても無理もないことです。
清太は労働という概念を理解していませんでした。これまで何不自由なく暮らしてきたため、生きるために働くという発想がなかったのです。
2. 現代的な価値観を持つ少年だった
清太は「自分のやりたいことをやる」という現代の若者のような性質を持っていました。戦中の苦しい生活のなか、やりたいことをやって生きることを決めた清太に対して、おばさんも生きるために仕方がない決断をしたのではないでしょうか
高畑監督は清太について「『火垂るの墓』の清太少年は、私には、まるで現代の少年がタイムスリップして、あの不幸な時代にまぎれこんでしまったように思えてならない」と語っています。
3. 妹への過保護な愛情が判断を狂わせた
清太が働かない理由、それは「節子」が居たからではないでしょうか。働く間に節子が嫌な思いをするのではないかと考え、働かずに節子と一緒にいることを選んだのだと思います。
清太は14歳という年齢で、4歳の妹を一人で守らなければならないというプレッシャーを抱えていました。この責任感が、逆に社会との協調を拒む原因となったのです。
清太がクズと言われる具体例と事例
西宮のおばさんとのエピソード
清太は学校にも行かずに働かない選択をした上、家事を手伝うこともなく、日中はゴロゴロ過ごすか節子と遊んでいたのです。態度も悪く、食事を出して貰ってもお礼もせずに文句をつける始末…
特に問題視されるのは雑炊のシーンです。おばさんは清太が雑炊をおかわりした際、お米を避け、汁物を多くよそってお茶碗を渡していました。自分たちの子供には「多くのお米が入るように」雑炊をよそっていました。
貯金があったにも関わらず活用できなかった
実は清太には、両親が遺した貯金が7000円(現在の価値で約1000万円)もありましたが、戦時下では物々交換が主流で、お金があってもあまり意味がなかったのではないでしょうか。お金があっても物が売っていないので、物々交換の方が効率が良かったのです。
現在の価値で約1000万円という大金を持ちながら、それを有効活用する知恵も社会性もなかった清太の未熟さが悲劇を招いたとも言えるでしょう。
同時代の他の少年との比較
ゲンなら(はだしのゲンの主人公)おばさんの手伝いしながら外で仕事して稼いでただろうし、それでもおばさんが意地悪するならクソ壺に落として出て行って別の家と仕事見つけるだろうし。ゲンは清太より年下だけど清太がゲンのように振舞えたなら悲劇は回避できただろう。ちなみに、昭和20年の旧制中学校への進学率は5割未満(昭和15年だと4割未満)。ってことは、清太と同い年の子どもは半数以上は既に働いていたってのは知識として持っておこう。
SNSやWebで話題の投稿とその分析
清太クズ論への支持
「大人になって気付いたこと西宮のおばさんが言ってることが正論で清太がクズだったということ」
引用:Twitter
この投稿は非常に多くの共感を集めました。大人になってから見直すと、おばさんの言い分に理があることに気づく人が多いようです。戦時下の厳しい状況で、働かない清太への批判は当然だったという見方です。
清太擁護論の反論
「清太だって辛いんだし、14歳の子供に何を求めているんだ」
引用:note
一方で、清太を擁護する声も根強くあります。この時代では、もっとお国のためにできることがあったかもしれませんが、節子のためと思ったかもしれません。まだ中2です。中2の彼に見通しを持って行動できたかというと疑問です。今、目の前にいる節子が大事なのですから。
監督の意図を理解する声
「高畑監督は現代の若者が清太に共感できるように作った」
引用:はてなブログ
高畑監督は、(1988年頃当時の)若者が清太に共感することを狙って本作を作っている。この意図を理解すると、清太のキャラクター設定の意味が見えてきます。
宮崎駿監督の指摘
「海軍の互助組織は強力で、士官が死んだらその子供を探し出してでも食わせるから有り得ない話」
引用:マグミクス
宮崎監督「海軍の互助組織は強力で、士官が死んだらその子供を探し出してでも食わせるから有り得ない話」と指摘しています。清太は本来、海軍将校の子供であるため、餓死という惨めな最期を迎えるのは、当時に詳しい人の目から見ても、やはりおかしいそうです。
これは物語の設定そのものへの疑問を提起する重要な指摘です。
自己責任論への議論
「清太の破滅は自己責任だったのか」
引用:Yahoo!ニュース
自己責任という言葉を当てはめるべきかは、そもそも微妙な話に思う。助かりたい意志がないと助からないというのはどうしてもある話で、清太の行動は意図的に助からない方向に進んでいる。
原作者野坂昭如が明かした衝撃的な真実
実は、原作者の野坂昭如自身が「清太は美化された存在で、実際の自分はもっとクズだった」と告白しています。
野坂昭如の懺悔の言葉
「自分は、火垂るの墓の清太のようないい兄では無かった。・・・恵子には暴力を振るったり、食べ物を奪ったり・・・」「泣き止ませるために頭を叩いて脳震盪を起こさせたこともあった」
ぼくはせめて、小説「火垂るの墓」にでてくる兄ほどに、妹をかわいがってやればよかったと、今になって、その無残な骨と皮の死にざまを、くやむ気持が強く、小説中の清太に、その想いを託したのだ。ぼくはあんなにやさしくはなかった。
原作と現実の違い
小説だと清太が空腹に耐えかねて、節子のための缶ミルクを飲んでしまうという描写がある。反戦とか、お涙ちょうだいとか、被害者意識とかじゃない。懺悔なんだよ、この作品自体
野坂昭如は実際には:
- 妹に暴力を振るっていた
- 妹の食べ物を奪って食べていた
- 泣き止まない妹を叩いて脳震盪を起こさせた
- 節子のような可愛らしい会話はなかった(実際の妹は1歳4ヶ月)
実際の妹は一歳四ケ月、これでは会話ができない。十六年生れということにし、急性腸炎で三日寝つき死んだ、前の妹と同年。あの妹が生きていたらと、はっきり残る面影をしのび、戦時下とはいえ、暮らしにゆとりがあって、ぼくは確かにかわいがった。この気持を、まったく異なる飢餓状況下に置きかえた
作品は贖罪の意味を持つ
「私は溺愛の父親だ。娘の麻央を抱くと、戦争の日、私が殺した幼い妹を抱くような気がする。当代一の色事師が告白する鮮烈の記憶」
野坂昭如にとって「火垂るの墓」は、妹を守れなかった自分への懺悔の作品だったのです。清太を理想化したのは、「せめて小説の中では優しい兄でありたい」という願望の現れでした。
高畑監督の制作意図と清太像
清太はしかし、自分に完全な屈服と御機嫌とりを要求する、この泥沼のような人間関係のなかに身をおきつづけることは出来なかった。むしろ耐えがたい人間関係から身をひいて、みずから食事を別にし、横穴へと去るのである。
全体主義への抵抗として描かれた清太
清太たちの死は全体主義に逆らったためであり、現代人が叔母に反感を覚え、清太に感情移入できる理由はそこにある」として、「いつかまた全体主義の時代になり、逆に清太が糾弾されるかもしれない。それが恐ろしい」
高畑監督は、清太の個人主義的な生き方を全体主義への抵抗として捉えていました。現代の価値観では理解できても、当時の価値観では受け入れられない存在として清太を描いたのです。
現代の観客への警鐘
たとえば、結果的に主人公の兄妹を追い出すことになるあの親戚のおばさんをみて、今の若い人は「ひどい」と思うだろうし、清太があの家をとびだす気持ちに全面的に共感するはずです。しかし当時の状態を経験した人は、あの程度のいやみは特別のことでもなんでもなく、ひどい「いじめ」といえるかどうかさえ怪しいことを知っています。
別の視点から見た清太の行動:擁護論
14歳という年齢の限界
この物語は、「4歳と14歳で生きようと思った」という衝撃的なキャッチフレーズで有名です。この通り、14歳(今でいう中2かな?)の清太が4歳の節子と二人で戦争中に必死で生き抜こうと思った物語です。
現代でも中学2年生に大人としての判断力を求めるのは酷です。まして戦時下という極限状況で、幼い妹を守りながら生きていくのは相当困難だったでしょう。
おばさんの対応にも問題があった
清太はおばさんに感謝の気持ちがないと言いますが、清太が持ってきた母親の着物をお米に変えたあと、そのお米を清太や節子に少ししか食べさせなかったのはおばさんです。そんな人の手伝いやまして、感謝の気持ちなど大人ですら出来ませんね?
清太たちが持参した着物や貯金で得た食料を、公平に分配されなかったという点では、おばさんの対応にも問題がありました。
社会システムの欠陥
清太は社会関係を断ったことによって、自助で頑張ろうとしました。しかし、だめでした。やっぱり、共助、公助は欠かせません。この映画で言えば、共助は叔母、公助は医者、あるいは、交番の警察でした。
個人の責任を問う前に、戦時下の社会システムそのものに問題があったという視点も重要です。
まとめ:清太はクズなのか?最終的な考察
清太がクズかどうかという問題は、実は「どの価値観で判断するか」によって答えが変わります。
戦時下の価値観では確実にクズ
当時の社会常識から見れば、清太の行動は確実に非常識で、批判されて当然でした。「火垂るの墓」の中ではおばさんの実娘だって国のために働いていました。つまり、その当時からすると清太が働かない姿は「まさしく異様」だったのです。
現代の価値観では理解できる部分も多い
しかし、現代の私たちから見れば、14歳の少年が4歳の妹を抱えて生きていくのは非常に困難で、完璧を求めるのは酷だとも感じられます。
原作者の意図は懺悔
最も重要なのは、原作者の野坂昭如が清太を理想化して描いたという事実です。現実の野坂少年は清太よりもさらに「クズ」だったと本人が告白しており、作品は贖罪の意味を持っています。
監督の意図は現代への警鐘
高畑監督は、現代の個人主義的価値観を持った少年が戦時下に放り込まれたらどうなるかを描きました。清太の行動を通して、時代や状況によって価値観がいかに変わるかを示したのです。
最終的な答え
清太は戦時下の価値観では確実にクズですが、それ以上に重要なのは:
- 戦争という状況が子どもたちをこのような極限状態に追い込んだ
- 時代によって価値観は変わるが、戦争の悲惨さは普遍的
- 個人の行動よりも、そうした行動を余儀なくされる社会システムの問題
という点です。
清太をクズと批判することは簡単ですが、なぜそうした行動を取らざるを得なかったのか、そしてそうした悲劇を生み出す戦争そのものを考えることが、この作品の真の価値なのかもしれません。
私たちは清太の行動を批判しながらも、同時に戦争の悲惨さと、時代に翻弄される人々の姿を忘れてはいけないでしょう。野坂昭如の懺悔の気持ちと高畑監督の警鐘、そして現代を生きる私たちの価値観、すべてが重層的に組み合わさって、この不朽の名作は成り立っているのです。